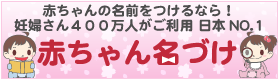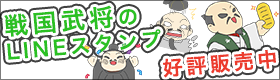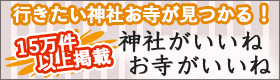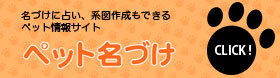掛川城(雲霧城・松尾城) 登城記録 (本多百助さん)
➀三の丸公園より
②大手門北の橋より
③圓満寺 掛川城移築蕗の門
掛川古城(天王寺城)
応仁の乱後、守護層の抗争が激しくなるにしたがい、今川氏は文明初年(1470年代)朝比奈備中守泰熈に築城させ掛川を守らせた。そして次第に城郭の拡張と強化をはかり、永正10年頃城の南西方の龍頭山に新城を築造した。
桶狭間の戦い(永禄3年・1560)後、領国支配の衰退と武田氏の駿府侵略により朝比奈氏の守る掛川城に逃れた今川氏真は永禄11年(1568)から翌12年にかけ徳川家康と戦い敗北した。掛川古城はこの合戦のとき徳川家康の本陣として使われた。
掛川古城は標高48mの龍胴山を最頂部として東西約400m、南北約300mの規模で主尾根上と派生した尾根上に曲輪を配置し、その南麓に館を設けている。主尾根は大堀切によって分断され、西側と東側に分けられそれぞれ曲輪をもつ中世の典型的な城郭である。主郭は大堀切の西側に配置し、上段、下段から成っている。上段北東隅から東側大堀切部分と南北部分に土居の一部が遺存している。主郭の西側には二つの曲輪を配置し、北側には腰曲輪が配置し、北曲輪に通じている。大堀切の東側には東曲輪をはじめ二つの曲輪が段階状に配置され、南側に腰曲輪を設けている。北曲輪は主郭の北側から派生している尾根を削平して築造し、城の搦手は北側の北池で備えとしている。居館は主郭の南側24m下の台地に設けてある。城館周囲の北側は水田、溜池となり、南側は逆川、東側に谷を隔てて笠町砦、西側には掛川城が所在する。遺跡の多くは道路、宅地などとなり消滅し、主郭、大堀切、東曲輪、腰曲輪の一部を残すのみである。
おすすめ度: ★★★★★
おすすめ度: ★★★★★







 日別アクセスランキング
日別アクセスランキング






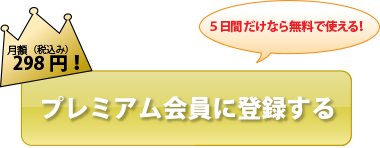

 新着更新
新着更新


 お城ニュース
お城ニュース